
旅行する際、どの観光地に行ったら良いか迷う方は多いと思います。この記事では鳥取県鳥取市やその周辺エリア(岩美町・智頭町・倉吉市・湯梨浜町・三朝町など)の観光スポットを紹介します!
目次
鳥取エリア
【日本三大砂丘の1つ】鳥取砂丘

鳥取砂丘は日本海沿いに南北2.4㎞・東西約16㎞広がる日本で最も有名な砂丘です。中国山地の花崗岩が風化して作られた砂が千代川によって日本海に流され、その砂が堆積して鳥取砂丘が形成。「すりばち」と呼ばれる高低差のある地形や風紋・砂簾などの砂漠に現れる模様、らっきょう畑や砂丘特有の植物などが見られることが特徴です。鳥取砂丘のうち「浜坂砂丘」と呼ばれるエリアが観光地化されており、鳥取砂丘会館・鳥取砂丘砂の美術館・チュウブ鳥取砂丘こどもの国などの施設があります。
【珍しい球体の石垣がある!】鳥取城跡

鳥取城は標高263mの久松山(きゅうしょうざん)一帯に築かれていたお城で「久松城」とも呼ばれていました。戦国時代に因幡守護であった山名氏によりこの地に初めて城が築かれ、1617年(元和3年)に池田光政が入城すると大規模改修が行われます。明治時代の廃城令により鳥取城の建物は解体されましたが、天守台や石垣が残されており、球体の石垣の「天球丸」は城郭で用いるのは珍しい巻石垣となっています。2021年(令和3年)に中ノ御門表門が木造復元されました。
【基本情報】 【交通アクセス】
【鳥取城近くに建つ洋風建築】仁風閣

仁風閣(じんぷうかく)は1907年(明治40年)に旧鳥取藩主である池田仲博の別邸や皇族の宿泊場所として建設され、1907年には皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)が御宿泊所として利用されました。フレンチルネッサンス様式の洋風建築で、2階からは宝隆院庭園を眺めることができます。現在は建物内で鳥取藩や池田家に関する資料展示が行われています。
【基本情報】 【交通アクセス】
【因幡国一宮・紙幣に掲載された社殿】宇倍神社

宇倍(うべ)神社は武内宿禰命を祀る旧国幣中社の別表神社で、因幡国一宮とされる格式の高い神社です。因幡国造の伊其和斯彦宿禰(いきわしひこのすくね)が成務天皇から賜った大刀を祀ったことが起源で、戦国時代以降は一時的に荒廃するも1633年(寛永10年)に池田光仲からの寄進を受けると再興しました。1899年(明治32年)に武内宿禰命と宇倍神社の社殿が五円紙幣に載ったことから、お金や商売繁盛の神様として信仰されています。境内の双履石(そうりせき)は武内宿禰の終焉の地とされています。
【因幡の白兎ゆかりの地】白兎神社

白兎(はくと)神社は日本神話に登場する『因幡の白兎』に登場するウサギとされる白兎神を祀る神社です。白兎神社が鎮座する丘は『因幡の白兎』においてウサギ皮膚を乾かした場所とされいることや、ウサギは大国主命と八上比売の婚姻を取り持ったという言い伝えから白兎神社は皮膚病の神様・縁結びの神様として信仰されています。
【基本情報】 【交通アクセス】
白兎海岸

(編集中)
【基本情報】 【交通アクセス】
岩美エリア
浦富海岸

浦富(うらどめ)海岸は日本海沿いに約15㎞広がるリアス式海岸です。日本海の荒波により浸食されて形成された花崗岩の奇岩・断崖・洞門などが見られるほか、大小さまざまな島々が浮かぶ光景が広がることから「山陰の松島」とも呼ばれています。夏頃の浦富海岸周辺は白イカの産卵地となっており、漁船が灯す漁火(いさりび)の風景も魅力的です。
【基本情報】 【交通アクセス】
智頭エリア
【近代和風建築の傑作】石谷家住宅

智頭は因幡街道の宿場町として栄え、鳥取藩最大規模の宿場だったそうです。石谷家は江戸時代は大庄屋を務め、明治時代以降は地主経営や宿場問屋を営んでいたそう。主屋を中心とし、座敷棟・家族棟・蔵など江戸時代から昭和時代にかけての建造物を多くを有し、これらの建物の保存状態が良好であることから国の重要文化財に指定されています。また池泉庭園・枯山水庭園・芝庭などで構成される石谷氏庭園は春と秋に特別開放されます。
倉吉・湯梨浜・三朝エリア
【石州瓦と白壁の町並み】倉吉白壁土蔵群(打吹玉川)

「倉吉白壁土蔵群」で知られる打吹(うつぶき)玉川地区は1300年から1600年頃にかけて打吹城の城下町として、江戸時代初期から大正時代までは商業として栄えました。石州瓦を持つ町家や白壁の土蔵の建物が多く見られる昔ながらの町並みが残されていることから、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。酒蔵や醤油蔵として使われていた建物をリノベーションした飲食店・喫茶店・ギャラリーなどが多く見られるほか、豊田家住宅・打吹公園・倉吉博物館・倉吉パークスクエアなど観光施設があります。
【基本情報】 【交通アクセス】
【日本最大の中国庭園】燕趙園

燕趙園(えんちょうえん)は姉妹都市関係である鳥取県と河北省(中国)の友好のシンボルとして、1995年(平成7年)に完成した日本最大規模の中国庭園です。名前は古代中国に存在した「燕」「趙」に由来。東郷湖を借景とした景色を楽しむことができるほか、中国の皇帝色である瑠璃瓦を用いた燕趙門、中国江南地方の風情を感じられる梧竹幽園などが見どころ。道の駅「燕趙園」が併設されており、二十世紀梨やしじみ(湯梨浜町名物)を購入できるほか、梨ソフト・牛骨ラーメンなどの鳥取県グルメをいただくことができます。
【伯耆国一宮・安産の神様】倭文神社

倭文(しとり)神社は建葉槌命(たけはづちのみこと)を祀る旧国幣小社の別表神社で、伯耆国一宮とされる格式の高い神社です。機織に携わったとされる倭文氏がこの地に御祭神を祀ったことを起源とし、出雲からやってきた下照姫命がこの地に船を着けて鎮まったことから、下照姫命は配神として祀られています。尼子氏や池田氏からの崇敬篤く、鳥取藩主の祈願所とされました。むかし難産に苦しんでいた女性が願かけををすると下照姫命が現れ、その後難産に苦しむ女性が岩の近くで出産をしたことから倭文神社は安産の神様として信仰されており、境内にはその言い伝えに因む「安産岩」があります。
【日本最大のラドン温泉地域】三朝温泉

倉吉市の南隣に位置する三朝町の三朝(みささ)温泉は約20軒の旅館・ホテルが集まる温泉地です。日本最大規模のラドン温泉地域として知られており、代謝促進・免疫力・治癒力向上などに効果があるとされているほか、三朝温泉の泉質は飲用にも適しておりミネラルが豊富で胃の粘膜力向上の効果があります。1164年(長寛2年)に源義朝の家臣であった大久保左馬之祐により発見され、「3つ目の朝を迎えるころには病が消える」という言い伝えから「三朝」と呼ばれるようになったそう。古くから本格的な療養温泉として知られており、周辺には温泉療法を実施する三朝温泉病院などの医療機関も見られます。
三佛寺





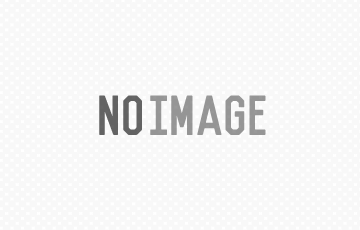





コメントを残す